『きく』という言葉には 意味が微妙に違う漢字が存在します。
『聞く』
意識しないでただ耳に入ってくる音を受け入れるという場合には「聞く」を使います。例えば次のように使います。
・教室の外から、車の音が聞こえてくる。
これは意識して車の音を耳にしているのではなくて、ただ勝手に耳に入ってくる音をきいているというシチュエー
ションですね。また、道をたずねるときにも「道を聞く」と使いま一方で「聴く」は、
積極的に意識して音に耳をかた
むける場合に使います。例えば次のように使います。
『聴く』
・クラシックのコンサートで素敵な演奏を聴いてきた。
これは、コンサートの音を意識してきいているというシチュエーションですね。授業を聴くやCDを聴くというように、
耳をかたむける音が決まっているような場合に使います 英語では「
聞く=hear」で「
聴く=listen」です。
以前 保育園でお集まりをしていた時、必ず前にいて 先生の話をじっと きいているような子がいました。
でも、意外と小学校に行ってから、内容を理解していなかったり、忘れ物が多かったりした事例がありました。
意外と、大人はシーンとしているとすべての子どもたちが きいてくれていると勘違いして、『あの時言ったで
しょうきいていなかったの?』と怒ったりすることがよくありますが、 子どもたちの 聴く力 にも 個人差が
ものすごくあるように思います。 まだ『わからない、なんで?』などリアクションがあると、よいのですが、分か
らなくても 『わかりましたか』の問いかけに、みんなと同じように『はい』と答える習慣だけがつくと、
分からなくても、分かっていても意見が言えない子になってしまうような気がして危惧しています。
幼児期 でいえることは、 子どもたちは、何か興味がありそうな話、いつも同じ内容で 同じ話し方でない
話 、わくわくした話 など
幼児の特性を理解して、いかに子どもたちを引き込んでいくか? 聞きたくなるような 話し方をするかが保
育士の専門性 の様な気がします。 そして、専門性に意外と大切なことは ユーモア にあふれていること
とです。 これは、政治家が講演中に ところどころ 小話(笑い話)をいれてくるようなもので
真面目な話を聞いてもらうための 心をつかむためのテクニック的な要素もあるのですが・・・
ユーモアは コミュニケーションにおいて 大人の社会でも、子どもの社会でも不可欠の様な気がします。
こどもの特性(発達)を十分理解していること(何に興味があって、何が好きで、何ができて、何が
怖くて・・など)が前提にありますが。
保育士の仕事は、子どもたちが将来あらゆる 職業につく 社会人になる事を
想定すると
様々な事に興味を持ったり、 常に社会人としてアンテナをはる必要があります、実は保育以外の仕事に
答えがあることもたくさんあるような気がします。
大人になって 聴く力がなぜ必要かというと、コミュニケーション能力においては、話す力がある人より
聴く力がある人の方が成功すると言われています。 聴く力とは、すべてを受け入れることではなく
自分にとって必要な情報をとりいれたり、またコミュニケショーンの場においては、相手が本当に伝えたい事
の真意を読み取ったり、何を言いたいのかを瞬時に理解したりする力であると思います。
幼少期に 毎日 先生がいったことを静かに聞くだけの経験 と幼少期に 様々な年代の様々な人たちと
話をした経験、ディスカッションした経験とでは どちらの経験が、
将来において 『聴く力』 をより育む 事になるのでしょうか??









.jpg)
.jpg)


![]()


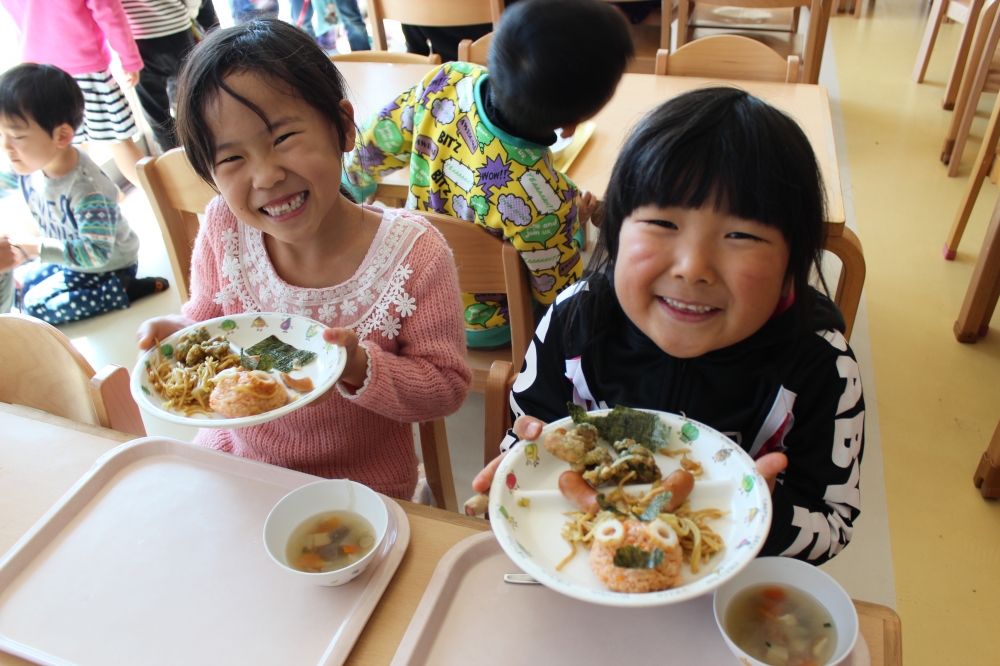

![]()













.jpg)

.jpg)






.jpg)



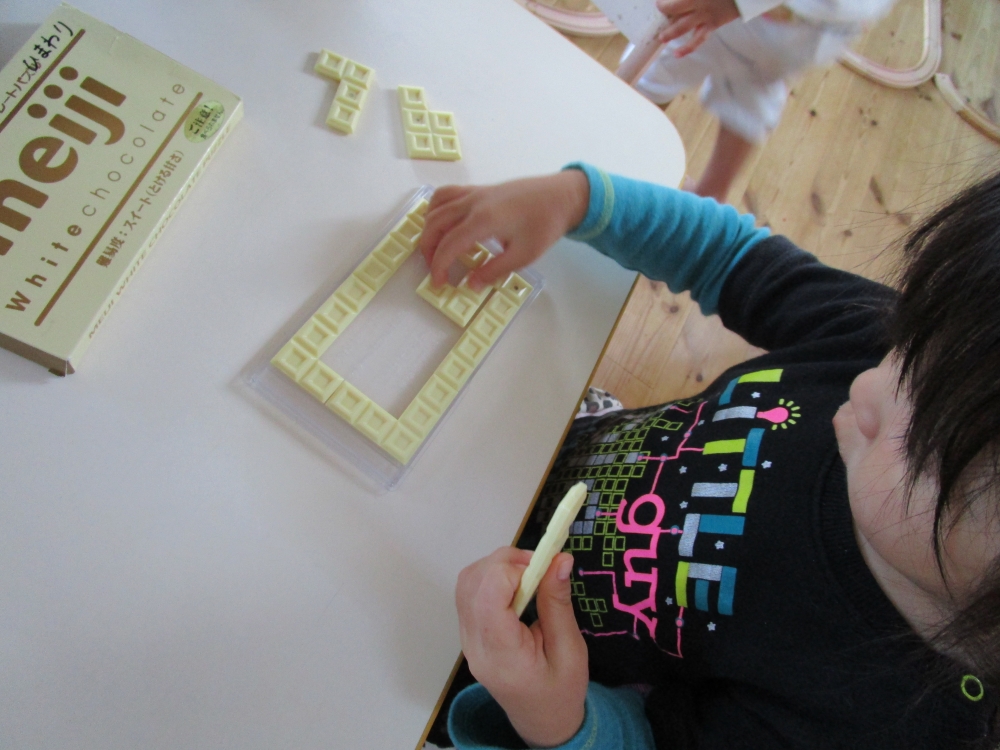






.jpg)

.jpg)





.jpg)


.jpg)
 』
』
.jpg)












.jpg)




.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)












.jpg)

.jpg)
.jpg)




